
すき焼きを作る時、入れる順番がおかしいからうまく作れないのかなー?
結局、ごった煮みたいになってしまう、どうしたら、見栄えのいいすき焼きが作れるの?
料理研究家、料理大好きフッくんです。
すき焼きを作るにあたって、入れる順番を意識するだけで、美味しいすき焼きを作る事が出来ます。
長い料理経験の中で、ご自宅で上手に出来るコツを伝授いたします。
味付けは出来るんだけど、うまくできない方はぜひ最後までみていって下さい。
基本的なすき焼きの具材の入れる順番は?


すき焼きには、関東風、関西風とありますが、まずは定番具材は何を入れるのか?入れる順番は何から入れるのか?をご紹介します。
基本的な具材は何があるの?
①牛肉(すき焼き用、肩ロース薄切り)
②焼き豆腐
③長葱
④しいたけ
⑤えのき
⑥しらたき
⑦春菊
⑧牛脂
⑨卵
⑩すき焼きのタレ
※関東では➡割り下 割り下の作り方はこちら👍
※関西では➡砂糖、醤油、みりん、酒
★白菜については、関西では入れる事がほとんどです。お好みで入れましょう。
すき焼きの定番の材料が揃ったら、材料を入れて作っていきます。
それぞれの具材の詳しい解説も紹介してるので、是非参考にしてみて下さい。👇
具材をいれる順番を見てみよう!
★関東風すき焼きの場合
~入れる順番~関東編~
①牛脂➡②牛肉➡③長ネギ➡④割り下
⑤しらたき➡⑥焼き豆腐➡⑦しいたけ➡⑧えのき➡⑨春菊
~解説~1,すき焼きの鍋を十分に温めて、牛脂を鍋全体にひく。2,牛肉、長ネギを入れて裏表焼く。3,具材が、全体の1/4浸かる位に、割り下を加える。4,しらたき、焼き豆腐、しいたけ、えのきを加えて、しんなりするまで煮込む。5,2回目の牛肉、春菊を加えて、しんなりしたら出来上がり。★牛肉は初めと最後(手順1と手順5)に2回分けて入れる
★関西風すき焼きの場合
~入れる順番~関西編~
①牛脂➡②牛肉➡③長ネギ➡④割り下
⑤しらたき➡⑥焼き豆腐➡⑦しいたけ➡⑧えのき➡⑨春菊
~解説~1,すき焼きの鍋を十分に温めて、牛脂を鍋全体にひく。2,牛肉を入れて、裏表の色が変わるまで焼く。3,鍋に直接、醤油・砂糖・酒を入れる。(みりんは、お好みで入れてください)4,水分の多い野菜(白菜)を最初に加え、しらたき、焼き豆腐、しいたけ、えのきを加えて、しんなりするまで煮込む。5,2回目の牛肉、春菊を加えて、しんなりしたら出来上がり。★牛肉は初めと最後(手順1と手順5)に2回分けて入れる
作り方の違いと言えば、割り下を使うか使わないか、白菜を入れるか入れないかです。
関西では、直接調味料を入れるので、お好みの味が作れますが初心者の方は難しいし、味にばらつきがあるので、割り下を使うことがオススメです。
割り下とは、醤油、砂糖、みりんなどを加えた合わせ調味料のことです。
割り下のレシピや具材のバリエーションを増やしたい方はこちらを参考にしてみて下さい👇
具材を入れる際の大切なポイント

余り場所を動かさずに、煮込むと言っても、難しいですよね。
それぞれポイントを解説します。
- ①底の広い奥行きの鍋を使用する
まずは、以下のような大きい、幅広い鍋が使いやすいです。↓参考にしてみて下さい↓
広い鍋で、すき焼きを作る事で、効率よく作業が出来ます。ご自宅である鍋で比較的大きい鍋を使用しましょう。
上記で紹介している鍋が一つあれば、色々活用できますし、値段もお手頃です。
広い鍋を使うことで、それぞれ具材を個別に調理でき、並べた時に、具材同士が混ざりにくくなります。
- ②お肉で旨みをつけ、最初と最後に2回に分けて入れる
最初に焼いて、ダシとする肉と完成前に入れる肉と分ける事で、美味しくなります。
ダシ用にはじめに少し入れ、葉物野菜の前に残りを追加で入れて調整してください。
※お肉をはじめに焼くのは、割り下に旨みや香ばしさを移すため。

焼くのもいいですが、お肉をバーナーで炙ればさらに美味しくなりますよ。
最初に炙るのがポイントですがバーナーは火傷に注意してくださいね。
ただ、他の肉は最後に入れて、柔らかさを楽しみましょう。
- ③野菜を入れる順番を意識する
基本的には、水分の多い食材から入れていきます。また、豆腐やしらたきのように、味をしみこませたい食材を先に入れましょう、
何ですが・・・ややこしいし、正直あまり意味がありません。
割り下の味が薄いから、白菜(白菜を入れる場合は)の水分でさらに薄くなるんです。
蓋をして、蒸し煮にした方が、簡単でうまくいきます。また材料をいじらないので、見栄えも良く仕上がります。
- ④しらたきの性質を知る事
②肉のそばには置かない
お肉の隣にこんにゃく、しらたきを並べないのは、こんにゃく、しらたきには石灰カルシウムが含まれているためです。
この成分が肉のタンパク質と交わり、熱凝固が早くなって、お肉が硬くなってしまうんです。
ただ、日本こんにゃく協会が、第3者機関である一般財団法人「食品環境検査協会」に委託して「しらたき」の有無による肉の硬さの比較試験を実施した結果、しらたきで肉が硬くなるというのは誤解となっています。
実際は、肉の種類や質のよって硬さが変わるので、気にせず入れましょう。
それよりも、こんにゃくは、アルカリ性食品なので、ごぼう、じゃがいも、さつまいも、れんこんなどと一緒に入れるとこんにゃくの色が変わる事が大事です。
含まれるポリフェールの一種、クロロゲン酸と反応すると、緑色や紺色などに変色する場合があります。
時間が経つと変色が進み、料理全体が変色してしまうので、すき焼きに入れる場合は、離して入れるようにしましょう。
実際、しらたきとごぼうを一緒に水で茹でると、変色します。
ただ調味料が入る事で、変色はほとんどしませんが、しらたきは一度茹でる事をオススメします。
~補足~
また、関西では、白菜を入れる事で水分がでます。そのため、醤油、砂糖で味を付けますが、割り下を使うことで、白菜の水分で薄くなるとよく言われます。
白菜を多く使う時は、別途、醤油、砂糖を足して味を調整するか、割り下を濃い目に作るといいでしょう。
また、市販の割り下は使い勝手は便利ですが、結構甘いので、甘いのが苦手な方は、醤油を足したほうがいいです。
また、野菜の水分で、味が薄くなりやすいです。
継ぎ足しもするので沢山使う事になり、コスト面も悪いので、割り下は作るのがオススメです。
結論、割り下を作るか、醤油を足しましょう。
濃い場合は、水で薄めれば解決します。薄ければ調味料を足せば解決できます。
それでも、味がぼやける場合は、ダシの素、麺つゆを少量足せば、整いますよ。
私は、肉を焼いた後、醤油、砂糖で味をつけて、白菜を入れた後にも、醤油、砂糖を入れて絡めます。
残りの野菜を入れた後に、割り下を入れて煮込めば、味が整います。白菜を入れる場合は、水分が出るので、割り下の量は少し減らします。
肉と野菜の具材の比率について

すき焼きを作るときに肉と野菜の割合が気になるという方も多いのではないのでしょうか。
ここでは、牛肉を基本にご紹介したいと思います。
牛肉を用意するときは、
①1人前100g~200gを用意する
②部位を選択する
③スライスのお肉を使う
牛肉は1人前100g~200g(150g前後)が適量と言われています。
ちなみにですが、お店では1人前100gで設定されています、また吉野家の並盛の肉の量は90gです。
目安は、
- 男性 200g
- 女性 150g
- 子供100g
を目安にするといいでしょう。
お肉が好きな人やたくさん食べたい場合には、少し物足りない量です。満足いくお肉を食べたい方は、300gあれば満足できますが、野菜と食べるのがすき焼きですので、お好みで調整してみてください。
部位についてよく使われるお肉は、
- リブロース(高価ですがお肉をメインに考えている方)
- 肩ロース(柔らかいのですき焼きには最適です)
- もも肉(あっさりした人には最適)
です。
また、しゃぶしゃぶの肉でもすき焼きはできますが、火を通しすぎずにいただくのがオススメです。
特に、子供や高齢者の方がいるご家庭では、しゃぶしゃぶにお肉は柔らかく食べやすいです。
お金に余裕がある方はいいですが、中には贅沢ができない方もおられます。
スーパーで売っているセール肉・細切れ肉を30分程煮込んでから、茹でた肉を焼いてすき焼きに入れると美味しくいただけますよ。
ブロック肉を30分程煮込んでスライスしたお肉を焼くのも一つの方法です。そうすることでしっとり柔らかくなるためです。
牛肉の安価なものは、お肉が固いのが多いので、逆に煮込んでから調理するのがオススメです。
野菜の比率は、肉1:野菜4の割合がオススメです。(決まりはありません)
野菜は種類によって重さも違うので、大体の量をご紹介します。
【1人前】
牛肉肩ロース 100g
白葱 20g(1本 60g)
白菜 80g(1/4玉 400g)
しらたき 100g (1P 200g)
生椎茸 2ケ(約20g)
春菊 40g (1束 200g)
人参(花形) 1枚(約5g)
【4人前】
牛肉(薄切り)600~700g
しらたき(糸コンニャク)…大1袋(約200g)
焼き豆腐…1丁
玉ネギ…1個(1個 200g)
白菜…1/4カット
白ネギ…2本 (1本 60g)
青ネギ(九条ネギ)…1袋 (70g)
春菊(菊菜)…1袋(1束 200g)
えのき茸…1袋(約100g)
椎茸…4枚 (1個 約20g 大約30g)
麩(丁字麩)…4~8個
白菜や玉ねぎは加熱すると少なくなるので、少し多めに入れるとバランスが取れます。
少し物足りない場合は、お肉を増やしたり、豚肉・鶏肉・鴨肉で代用するといいでしょう。
すき焼きはいろいろな具材を入れることができるので、自分なりのすき焼きに挑戦してみてください。
まとめ。。。
入れる順番を詳しく解説しましたが、関西、関東と比べるとややこしくなりますよね。
割り下があると味が安定して失敗がなく、味が極端に変わらないので、調理しやすい鍋を用意して、割り下を使うことで、失敗なく作れると思います。
割り下もご紹介していますので、是非参考にしてみて下さいね。
注意点は、ご紹介しましたが、あまり意識しすぎないが大事です。
しらたきも、基本の具材で作れば全く問題ないので、心配せず具材を投入しましょう。
他にも、すき焼きの変わり種や具材についてご紹介していますので、参考にしてみて下さいね。





































































































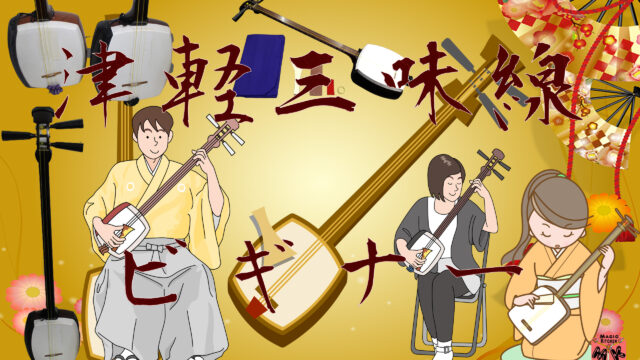

























👇お気軽にコメントしてね👇
具材のおもさの比があるとよい
コメントありがとうございます。
肉と野菜入れる割合を追加しましたのでまた参考にしてみて下さい。